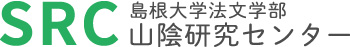山陰地域伝存の古典籍資料に関する基礎的調査研究
山陰研究プロジェクト0401
期 間:2004-2006年度
代 表:蘆田 耕一 (法文学部教授・日本文学)
目的
山陰地域、特に出雲地方は『古今集』によれば和歌発祥の地であるとされており、そして奈良時代に六十余国に提出が命じられた「風土記」のうち、完全な形で現存するのは『出雲国風土記』だけである。また、出雲大社の存在も無視できない。
このように、文化的に豊かな山陰地域には今まで調査がなされず死蔵された貴重な古典籍資料が存することは確実であろう。これらを掘り起こして詳しい調査をすることによってその一端が明らかになってくると思われる。まずはじめに、各図書館や旧家を調査して目録作りから着手し、当テーマに関わるホームページを作成したい。
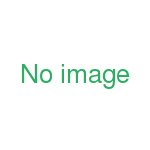
研究発表・報告
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
進捗状況
◆2006年度の研究計画と目標
- 前年度に引き続き、各図書館および手銭家の調査を行う。手銭家の完全な目録を完成させる。
- 東京の国文学研究資料館で、前年度に引き続き、調査・収集する。
- 新規に出雲市立中央図書館(予備調査済み)の本格的調査を実施する。
- 六月に刊行した『出雲国名所歌集-翻刻と解説-』を基にして、これに類する刊行に向けて協議する。
- 古典籍の保存継承、調査研究のための地域ネットワーク作りの第一歩として当テーマに関わるホームページを作成する。
◆2005年度進捗状況
- 次の施設で、主に前年度に引き続き、資料の調査収集を行った。
- 島根大学附属図書館本館、および医学分館。 特に後者は安来の医師大森三楽の蔵書調査で、医学書、文学書、儒書等の多岐にわたることが判明した。
- 鳥取県立図書館の橋本栗谿文庫(儒学資料が中心)を調査した。
- 大社町の素封家手銭家において、手銭さの子手沢本の和歌や俳諧資料の細かな調査を行い、簡単な目録を作成した。
- 東京の国文学研究資料館で、主に出雲地方に関する和歌資料を調査し、紙焼写真で収集した。
- 『出雲国名所歌集』の翻刻のための最終調査を行い、執筆した。
研究参加者
※プロジェクト代表者は★を付す。
- 蘆田 耕一 (法文学部教授・日本文学)★
- 田中 則雄 (法文学部助教授・日本文学)
- 戸崎 哲彦 (法文学部教授・中国文学)
- 要木 純一 (法文学部助教授・中国文学)
- 蒲生 倫子 (大社町立図書館司書・図書館学)
- 道坂 昭廣 (京都大学大学院助教授・共生文明学)
(6名)