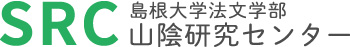出雲鰐淵寺の歴史的・総合的研究
山陰研究プロジェクト0703
期 間:2007-2008年度
代 表:小林 准士(法文学部准教授:歴史学)
井上 寛司(島根大学名誉教授)
目的
「融通無碍な多神教」と称され日本の宗教は、世界的にも極めて特異な位置を占めている。こうした宗教構造が一個の体系性を持った形で整えられたのは平安末・鎌倉初期のことで、それは、日本に固有の宗教施設である神社と寺院との機能分担に基づく相互補完関係(「神仏隔離」原則を踏まえた「神仏習合」)として成立した。
日本の中世にあって、この特異な宗教構造を最も象徴的な形で示しているのが、「国中第一の霊神」出雲大社と「国中第一の伽藍」鰐淵寺との関係であるところから、これを鰐淵寺に視点を据えることによって解明しようとするのが本研究である。文献史学・建築史・美術史・考古学・自然科学の5つの分野から、総合的な検討を試みたいと考える。
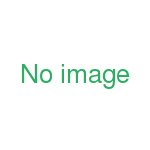
研究発表・報告
- 2008年度
- 2007年度
進捗状況
2008年度
◆昨年度の進捗状況
昨年度は、研究を進めるための基礎的準備ということで、これまでの研究の到達点の確認と、調査・研究を進めるべき論点や研究方法などについて検討を行い、ほぼその基礎的条件が整った。そこで、本年度から具体的な調査・分析に取り組むことにしたいと考える。
なお、上記の作業を通じて、問題をより明確にするためにもテーマをさらに絞り込んだ方がよいとの判断から、昨年度のテーマ「出雲鰐淵寺の総合的研究」を「出雲鰐淵寺の歴史的・総合的研究」に改めることとした。
◆本年度の研究計画と目標
- 上記の目標を達成するため、以下の事業を行う。総額40万円。
- 2泊3日の予定で、第1回目の鰐淵寺悉皆調査を行う。寺内に所蔵されている古文書(聖教類を含む)や仏像・絵画・仏具類、あるいは棟札などの所在確認を行い、その仮目録を作成する。
- 鰐淵寺周辺に所蔵されていると考えられる鰐淵寺関係文書の調査。近世・近代史料が中心になると考えられる。
- 出雲市役所文化財課と協力しながら、可能な範囲で鰐淵寺及び鰐淵寺周辺の考古学的調査を行う。旧寺域の確定のための調査であるが、予算的な制約もあるため、ごく初歩的で基礎的な調査に止まらざるを得ないと考える。
2007年度
◆昨年度の進捗状況
本年度から開始のプロジェクトである。
◆本年度の研究計画と目標
- 7月末に1泊2日の日程で全体会を開催し、次の点について作業を行う。
1)各研究班の作業分担の内容やあり方の確認
2)今後の作業の進め方についての検討
3)科研の申請方法や内容の検討
4)鰐淵寺にて現状の確認とともに、出来る範囲での調査の実施
5)寺宝類(古文書・仏像など)が移管されている古代出雲歴史博物館にて、 現状の確認と必要な調査の実施
なお、この会合の開催には出雲市役所の協力を得て、会場は出雲市平田の平田支所を使わせて頂くとともに、鰐淵寺への送迎についても出雲市役所のマイクロバスを使用の予定である。 - 今年度は、上記の点を踏まえて、各研究班ごとにこれまでの研究成果を総括し、今後の調査・研究課題とその方法について検討を行うことが目標となる。
- 以上の点を踏まえ、秋以後に講演会を開催するなどして、この総合的調査・研究の意義を広く市民にアピールするよう努めたいと考えるが、詳しい日程や内容については、今後検討を進めていくこととしたい。
研究参加者
※プロジェクト代表者は★を付す。
- 井上 寛司(島根大学名誉教授、文献史学)★
- 小林 准士(法文学部准教授、文献史学)★
- 平 雅行(大阪大学大学院教授、文献史学)
- 久留 島典子(東京大学史料編纂所教授、文献史学)
- 山岸 常人(京都大学大学院准教授、建築史)
- 田中 哲雄(東北芸術工科大学教授、庭園史)
- 関根 俊一(帝塚山大学教授、美術史・仏具)
- 浅湫 毅(京都国立博物館主任研究員、美術史・仏像)
- 松浦 清(大阪工業大学准教授、美術史・仏画)
- 的野 克之(島根県立美術館学芸グループ課長、美術史・仏像)
- 大橋 泰夫(法文学部教授、考古学)
- 松本 岩雄(島根県立古代出雲歴史博物館学芸部長、考古学)
- 花谷 浩(出雲市観光部次長兼文化財課学芸調整官、考古学)
- 鳥谷 芳雄(島根県立古代出雲歴史博物館専門学芸員、考古学・金石文)
- 小椋 純一(京都精華大学教授、植生学)
- 山内 靖喜(島根大学名誉教授、地質学)
(16名)