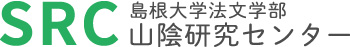患者・住民参加を重視した地域包括ケア研究
山陰研究プロジェクト1001
期 間:2010-2011年度
代 表:杉崎 千洋(法文学部教授・医療福祉論)
目的
島根県内の地域包括ケア、とくにがん患者や住民の参加を重視した地域包括ケア事例を取り上げ、以下の2つの研究を行う。
① 地域包括ケア政策決定への患者・住民参加研究
県がん対策推進計画の決定、評価における患者・住民参加の成果とその要因などを明らかにする。
② 地域包括ケアの臨床における患者・住民参加支援研究
がん患者の治療・支援計画決定への参加と、医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、がん患者会などによる患者のエンパワメントとの関連を明らかにする。
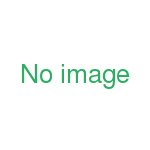
研究発表・報告
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
進捗状況
2011年度
◆2011年度計画
今年度も、主にがん患者支援に関する政策、臨床における患者・住民参加研究を2つの柱に沿って行う。昨年度の成果を踏まえ、研究の柱(の名称)は一部変更する。
表1は、地域包括ケアにおける患者・住民の参加の次元と地域包括ケアを構成する主要な主な分野をまとめたものである。参加には、政策、組織、臨床の3つの次元がある。地域包括ケアの主要分野は、医療および社会福祉・介護の2つとした。研究の柱①は、政策の次元、②は臨床の次元の研究を行う。
|
|
医療 |
社会福祉・介護 |
||
|
① |
政策 |
県 |
杉崎(A)・正野(B) |
━ |
|
市町村 |
━ |
加川(C) |
||
|
組織 |
━ |
━ |
||
|
② |
臨床 |
治療・支援 |
金子(D)・中村(E) |
|
|
コミュニケーション |
小野(F) |
|||
表1 研究の柱
① 地域包括ケア政策決定への患者・住民参加研究
地域包括ケアのうち地方自治体レベルの医療政策は県(A,B)の所管であり、社会福祉・介護政策は市町村(C)の所管である。それぞれの政策決定における患者・住民参加の検討を行う。① 地域包括ケアの臨床における患者・住民参加支援研究
臨床における治療・支援計画作成への患者参加(D,E)と、その基礎的部分として地域包括ケアでの医療・福祉と患者・住民のコミュニケーション(F)について研究を進める。
研究成果は論文などにまとめ、公表する。
2010年度
◆年度計画
① 高齢患者の退院後の社会参加研究
文献研究、専門職・患者らへの聞き取りなどにより、社会参加ニーズ調査の枠組み、視点の精緻化をはかり、調査を行う。② 患者・住民参加型の地域包括ケアシステム構築研究
患者グループ(がんサロンなど)、専門職、行政への聞き取り、住民へのこの地域の医療・福祉サービスに関する意識調査を行い、それぞれから見た患者・住民参加の成果と課題を整理する。①②共通 科学研究費補助金(基盤研究)を申請する。
◆進捗状況
主にがん医療に焦点を当て、研究を行った。その理由は、島根県は2つの点でこの分野の先進地域だからである。1つは患者の自助グループであるがんサロンの活動であり、もう1つはがん医療、がん患者支援に関する政策決定、実施・評価への患者参加である。
研究の2つの柱(下記、「◆2010年度計画」参照)に沿い、主に3つの調査を行った。
- がん患者支援を行っている医療ソーシャルワーカーと看護師、がんサロン責任者らに、がん患者の社会参加ニーズに関する聞き取りを行った。
- 地域包括支援センターなどによるがん患者などを対象とした地域包括ケアシステム構築に関する情報収集を、地域包括支援センター職員、ケアマネジャーらに行った。
- がん対策推進協議会の患者委員、担当県職員にがん患者の政策決定への参加に関わる聞き取り調査などを行った。
以上により、がん患者らの社会参加支援の基盤となる多職種チーム形成は今後の課題となっていること、また、がんサロンでは患者の社会参加支援はそれほど行われていなことが判明した。加えて、島根県レベルでは政策決定および評価への患者参加が進んでいること、とくに評価段階への患者参加は他に例がないことが明らかになった。一方、地域包括ケアシステム構築や病院組織運営への患者参加は、ほとんど進んでいないことが明らかになった。
研究参加者
※プロジェクト代表者は★を付す。
- 杉崎 千洋(法文学部教授・医療福祉論)★
- 加川 充浩(法文学部准教授・地域福祉論)
- 金子 努(県立広島大学保健福祉学部教授・ケアマネジメント論)
- 中村 明美(武庫川女子大学文学部専任講師・医療福祉論)
- 小野 達也(大阪府立大学人間社会学部准教授・地域福祉論)
- 正野 良幸(京都女子大学家政学部助教・福祉行財政論)
(6名)