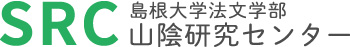石見銀山領における人口増加開始期における再生産機構に関する研究〔科学研究費プロジェクト〕
[科学研究費プロジェクト]
期 間:2007-2009年度( 3年間 )
代 表:廣嶋 清志 (法文学部教授・人口学)
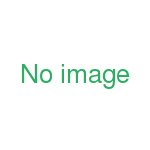
研究会・報告会
概要
◆目的
人口は社会の基本構造をなすものであり,その動態の転換は社会の基本的な変化を意味する。従来,日本の近代的人口転換(出生率・死亡率の低下の開始)は1920年ごろとされてきたが,より以前に起源を求める研究も現れている。すでに江戸時代末期の人口は多くの地域で停滞から増加へと転換し始めたが,それを引き起こしたメカニズムは未解明である。
本研究では,石見銀山領の各村の人口増加率の差は,主として出生率,死亡率,移動率のどれによるものか,またその差を生み出す結婚,家族構造およびその背後にある経済・社会の差異とどのように関わっていたかを,銀山および鑢製鉄という特徴ある産業を中心に,商業・漁業など多くの異なる産業を持った100余りの村,人口20-30万の地域の範囲で総合的に明らかにする。
これによって近代人口転換がどのような経済・社会変化と関わって開始されたかを明らかにする1つの事例とすることができる。
◆本研究に関係するこれまでの準備状況など
2004-2006年度の山陰研究プロジェクト参加者を主要な参加者とする。
研究成果
研究参加者
※プロジェクト代表者は★を付す。
- 廣嶋清志 (法文学部教授・人口学)★
- 田籠博(法文学部教授・国語史学)
- 小林准士(法文学部准教授・日本近世史学)
- 相良英輔(教育学部教授・日本史学)
- 山崎亮(教育学部教授・宗教民俗学)
- 伊藤康宏(生物資源学部准教授・農業経済学)
- 鳥谷智文(松江工業高等専門学校准教授・日本史学)
- 仲野義文(大田市立石見銀山資料館館長・学芸員・日本史学