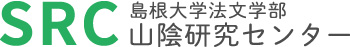石見銀山領における人口増加開始期における 人口再生産機構に関する研究
最終報告書(2007-09年度)
◆『宗門改帳からみる山陰の近世社会』その3(2010年3月発行)
- はしがき(廣嶋清志)
- 研究の概要
- 家の再生産と結婚率・出生率
―幕末石見銀山領の宗門改帳から見る(廣嶋清志) - 幕末石見銀山領における移動と就業―熊谷家宗門改帳から見る(廣嶋清志)
- 「宗門人別改帳」に見る明治初期の銀山町の様相(仲野義文)
- 近世後期たたら設備の貸借と契約―「懸り受け議定」の分析―(相良英輔)
- 松江藩鉄師頭取田部家文書の概要
~田部家古文書調査から知りえたこと~ (相良英輔) - 『宗門帳』所載人名の分析(田籠 博)
- 石見地方の「森神」をめぐって
―明治初年「神社書上帳」を手がかりに―(山﨑 亮) - 【史料紹介】一家一寺制に関する触書と関連史料の紹介(小林准士)
- 山内の様相と人の動き―八重滝鈩を中心として―(鳥谷智文)
- 博覧会時代の「漁業図解」-出雲石見と因幡伯耆の「魚漁図解」(伊藤康宏)
- 研究会記録
※上記のファイルを閲覧するにはAdobe Readerのインストールが必要です。
2009年度研究成果
◆2009年度の研究成果
『統計』2009年7月号(2009年7月発行)
※上記のファイルを閲覧するにはAdobe Readerのインストールが必要です。
2008年度研究成果
◆2008年度の研究成果
2007年度研究成果
◆2007年度の研究計画と目標
- 本年度、3回(5月、9月、1月)研究会を開催し、研究を進める。
- 島根大学所蔵の石見銀山領の熊谷家文書内の宗門改帳(文久3年、4年、69村)を電子化したファイル(人口約3万人分)の借用許可を麗澤大学に申請する。
許可された場合、このファイルを全面的に利用する研究を行う。
万日、許可されなかった場合、これ以外の村についてこの研究グループがすでに作成した電子ファイルを利用するとともに、さらに各村に分散して存在する宗門改帳のデータを発掘、入手して、解読、電子ファイル化して、順次研究に利用する。
以下、おおむね上記ファイルが許可されるものとして計画を立てる。- 石見銀山領およびその周辺における各村の人口について量、属性を確定し(各村の宗門別の宗門帳の欠落の有無、村の主要産業の推定)、村落間の関係を明らかにする。
- 性・年齢・配偶関係などの偏りの人口学的観察から、データ処理方法を評価する。
- 人口学的分析により宗門別の出生率較差を測定する。この結果と日本史学・宗教民俗学的な研究との突合せを行う。
- 宗門改帳の名前の特徴を日本語学的に分析し、地域差の計測方法を開発し、地域差分析の準備を行う。
- たたら山内、銀山町、漁村、農村等を産業歴史学的に分析し、それぞれの村の社会構成と村の相互関係を明らかにする。
◆2007年度の研究成果
その他論文・報告書等
◆『宗門改帳からみる山陰の近世社会』その1(2006年3月発行)
- はしがき(廣嶋清志)
- 第1章:江戸時代における銀山町の人口動向と社会構成について(仲野義文)
- 第2章:大吉鈩の変遷と山内人口の様相(鳥谷智文)
- 第3章:19世紀櫻井家たたら山内の人口動態(相良英輔)
- 第4章:東来海村の宗旨証拠帳から分かること (小林准士)
- 第5章:数え年年齢を使った計算について(廣嶋清志)
- 第6章:宗門別出生率の研究について(廣嶋清志)
- 第7章:近代島根の中山間地の農家・農村経済
―島根県邑智郡3か村『農事調査報告書』を通して-(伊藤康宏) - おわりに
- 資料一覧
◆ 『宗門改帳からみる山陰の近世社会』その2(2007年3月発行)
- はしがき:(廣嶋清志)
- 第1章:石見銀山附地役人の身分と通婚、家族(仲野義文)
- 第2章:石見銀山領の社会階層別出生率と結婚率
―持高別・宗門別較差を中心として(廣嶋清志) - 第3章:櫻井家「召抱人」の構成
―『明治弐巳十月 召抱人別書出帳』(櫻井家文書)の分析(鳥谷智文) - 第4章:町村是(農事調査報告書)調査の展開
―山陰地域を中心に―(伊藤康宏) - 第5章:『出雲国産物帳』の樹木方言記事について(田籠博)
- 第6章:墓上施設の現在(山崎亮)
- 第7章:たたら製鉄業における山内の人口動態と山内「掟」(相良英輔)
- おわりに
◆『たたら製鉄・石見銀山と地域社会―近世近代の中国地方―』(2008年3月発行)
※上記のファイルを閲覧するにはAdobe Readerのインストールが必要です。